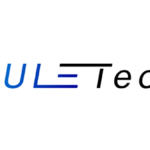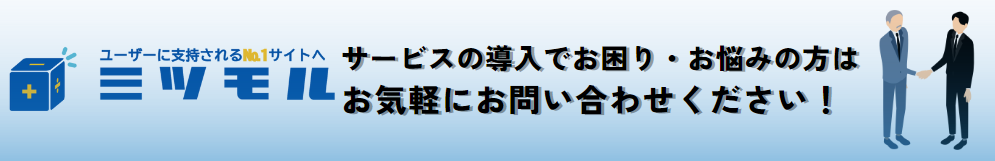電話対応はビジネスシーンにおいて避けて通ることができない業務です。
昭和の時代は、家の固定電話や公衆電話から離れている人と連絡するのが一般的でした。
たしかに、携帯電話やポケベルなどもありましたが、特に携帯電話は高額だったため、使用する割合は固定電話や公衆電話の方が多かったです。
しかし、令和になった近年においてはインターネットが広く普及し、IT技術も浸透しているため、あえて電話で連絡する必要がなくなりました。
例えば、スマホでチャットをしたり、メールで連絡をしたりすることができるので、新卒者の中には電話に慣れていない人も珍しくありません。
電話対応のマナーが悪い場合、会社の信用が失墜する可能性もあり、電話対応マニュアルの構築を検討している企業もあるのではないでしょうか。
この記事では電話対応マニュアルについて詳しく紹介するので、興味のある方はぜひ参考にしてください。
目次
電話対応する際に必要な事前準備
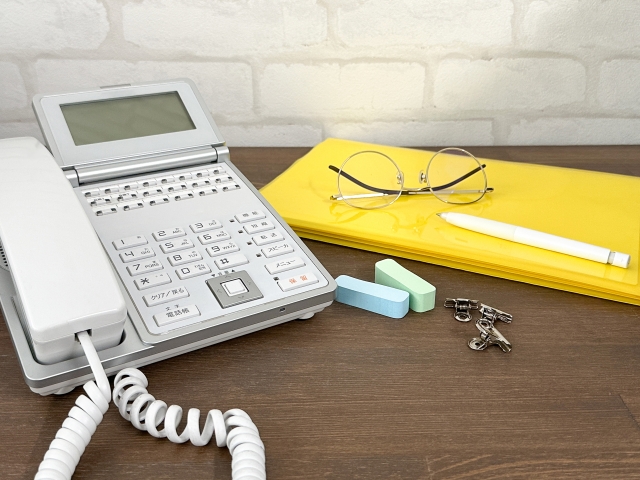
電話対応をする際に必要な事前準備は3つです。
事前準備を知ることで、スムーズな受け答えや好印象を与える対応ができるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
メモを取れる環境を整える
1つ目はメモを取れる環境を整えることです。
何に対して電話対応をするのかで異なりますが、お客さんから言われたことをメモする機会は非常に多いです。
例えば、お問い合わせ番号や電話番号など、口頭では覚えられない内容を聞くことは珍しくありません。
また、要件を尋ねてそれを整理するためにメモを取る方も少なくないでしょう。実際、電話対応の上手い人の多くがメモを取れる環境を整えています。
メモできる環境は電話対応において非常に重要なので、必ず整えておくことをおすすめします。
明るいトーンで話すように意識する
2つ目は、明るいトーンで話すように意識することです。
電話の第一印象は、聴覚情報で決まる可能性が高いです。そのため、明るいトーンで話すように意識すると相手に好印象を与えることができ、気持ちの良い電話対応になります。
電話をする前から明るいトーンで話すように心構えと練習をしておくのがおすすめです。
自分が会社の代表であることを意識して話す
3つ目は、自分が会社の代表であることを意識して話すことです。
電話対応はその会社の声として顧客は判断します。そのため、従業員として話すのではなく、会社の代表として話すようにしましょう。
そうすることで、話し方に自信を持つことができるようになり、説明に説得力が出ます。
電話を受けるときに使える電話対応マニュアル

早速、電話対応マニュアルを例文テンプレート付きで解説していきます。
まずは、電話を受けるときの電話対応マニュアルから紹介します。
受話器を取るタイミングとはじめの電話対応
電話がかかってきたあとに受話器を取るタイミングは、それぞれの企業で異なります。
基本的には早く出た方が好ましいとされていて、1コールで出ても問題ありません。
多くの企業では、3コール目までに受話器を取るようにマニュアルで定めているところが多いです。
3コール目までに受話器を取ることができたときは、下記のように自分から先に名乗るのが一般的です。
『お電話ありがとうございます。株式会社○○の〇〇でございます。』
3コール以上鳴ってしまったときは、待たせてしまっているため、一旦お詫びするようにしてから名乗るようにします。
『お待たせいたしました。株式会社○○の○○でございます。』
紹介した内容は一般的なマニュアルの例です。
コール数まで細かく明記しない企業もあれば、秒数で対応を変える企業もあります。あくまでも一例として参考にしてください。
相手が名乗ったら復唱して必ずメモを取る
相手が名乗ったら復唱して社名や担当者名、用件を必ずメモするようにしましょう。
復唱することで名前の聞き間違いなどを防げるため、非常に重要です。
社員の中には復唱はしてもメモを取らないという方も少なくありません。しかし、聞いた話の内容を長期間覚えるためには、メモが重要です。
また、メモをしないと伝言ミスなどが発生する可能性もあるため、先方に迷惑をかける恐れがあります。
相手の名前を復唱するときの例は、下記の通りです。
『いつもお世話になっております。株式会社○○の○○様でいらっしゃいますね』
もし、電話をしてきた方が名乗らなかった場合、社名や名前を聞くのが一般的です。
『恐れ入りますが、御社名とお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。』
また、名前だけを名乗った場合、下記のように返答します。
『○○様、差し支えないようでしたら御社名をお伺いしてもよろしいでしょうか。』
電話越しが騒がしく、名前を聞き取れないこともあります。そのようなときは、もう一度名前を聞いて確認するようにしましょう。
『大変恐れ入りますが、お電話が少し遠いようですので、もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。』
このように、それぞれの状況に合わせて適切な返答を選択し、復唱してメモを取るようにしましょう。
電話の取り次ぎは保留で対応する

電話の取り次ぎが必要なケースは多くあります。
取り次ぐ際、担当者が自分の近くにいる場合でも一旦保留にするのが一般的です。また、自分への電話で相談が必要なときも保留にして先輩に指示を仰ぐようにしましょう。
取り次ぎをする際は、下記のように担当者名を復唱したあとに保留ボタンを押します。
『弊社の○○でございますね。少々お待ち下さい。』
また、担当者の名前が聞き取れなかったときは、再度聞き直します。
『大変恐れ入りますが、もう一度担当者の名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。』
取り次ぐときは、担当者に対して下記のように伝えます。
『株式会社〇〇の○○様からお電話です。』
取り次ぐ担当者がクライアントの対応をしているときや少し席を外しているときは、保留の時間が長くなります。少し待たせているときは、保留を解除し、電話で状況を伝えるのが基本です。
『大変申し訳ございません。今担当者が少し席を外していますので、もう少しお待ち下さい。』
また、数分で対応できないときは、下記のように折返し電話をかけ直すのも1つの方法です。
『お待たせして誠に申し訳ございません。お調べするのに時間がかかっておりますので、お調べしたあとに折り返しのご連絡を差し上げてもよろしいでしょうか。』
電話の取り次ぐ際は保留にするのが基本です。また、保留が長くなるときは、定期的に解除して状況を伝えることも重要です。
短時間で取り次ぎができないときは、再度電話をかけ直すなど、相手に配慮するようにしましょう。
担当者が不在の場合の対応
担当者が不在のときは、保留を解除してその旨を伝えるのが一般的です。
不在の場合の対応は、一旦待たせたことを謝りましょう。その後、担当者が不在である旨を伝達し、担当者から折り返し電話を差し上げることを伝えます。
また、不在理由だけでなく、対応可能な時間や相手の連絡先を聞いてメモすることも重要です。
担当者が外出中もしくは会議中でその旨を伝えるときの例文は、下記の通りです。
『大変お待たせしてしまい誠に申し訳ございません。現在、○○は只今外出中です。○時頃に帰社する予定ですので、折返しお電話差し上げるようにお伝えしておきます。恐縮ではございますが、対応可能な時間帯とご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか。』
また、折返しが不要と言われたときは、担当者に伝言する旨を伝えます。
『かしこまりました。株式会社○○の○○様から電話があったことを○○にお伝えしておきます。』
電話が切れたあとに受話器を置く
相手が先に電話を切ってから受話器を置くのが一般的です。こちら側から先に電話を切ってしまうとマナー違反になります。
しかし、どうしても相手から電話を切ってくれないときは、電話でのやり取りが終わったことを下記のように伝えるのが一般的です。
『お電話ありがとうございました。失礼いたします。』
伝言メモを担当者に渡す
無事に電話を終えることができたら、伝言メモを担当者に渡します。
伝言メモには、下記の内容を記載すると分かりやすいでしょう。
- 日付
- 企業名及び担当者名
- 用件
- 電話番号
- 電話受け答え可能な時間帯
- 折返しが必要かどうか
- 自分の名前
担当者がいないときに伝言メモをデスクに置くと、紛失したりやそのメモに気づかなかったりする可能性があります。
そのため、担当者が帰ってきたときに電話があったことを口頭で伝えるのがベストです。
「もしもし」と電話に出ない
プライベートの電話であれば問題ないですが、ビジネスシーンで「もしもし」と電話に出るのはマナー違反に当たります。
「もしもし」はカジュアルな場面でしか基本的には使いません。顧客や取引先との電話で「もしもし」を使わないように気を付けましょう。
電話対応をする際は、「お電話ありがとうございます。」と出るのが一般的です。
電話をかけるときに使える電話対応マニュアル

次に、電話をかけるときに確認したい電話対応マニュアルを例文テンプレート付きで解説します。
マナーや言葉遣いなどをおさらいすることができるので、ぜひチェックしてみてください。
事前に用件を整理する
電話をかける前に用件を整理しましょう。
伝えたいことが明確になるため、相手にも理解してもらいやすくなります。
用件を頭の中で整理するのではなく、メモをしておくとより分かりやすいでしょう。
昼食時や業務時間外の電話は避ける
基本的に業務時間外に電話をかけるのはマナー違反です。
しかし、どうしても取り次ぎが必要な場合は、下記のように一言添えるようにします。
『夜分遅く(朝早く)に大変申し訳ございません。株式会社○○と申します。』
また、企業によっても異なりますが、昼食時は休憩中の社員もいます。業務時間外と同様に、できるだけ避けるのがマナーです。
昼食の時間は1時間程度なので、その後に電話するようにしましょう。
社名や名前を相手に伝える
電話がつながったら、社名と名前を下記のように名乗ります。
『いつもお世話になっております。株式会社○○の○○と申します。』
また、取り次ぎをする際は、そのあとに担当者の名を伝えます。
『○○様はいらっしゃいますでしょうか。』
電話をかけたときだけでなく、取り次ぎしてもらい電話の相手が代わったときも自分の社名と名前を名乗ることがポイントです。
そうすることで、相手から自分の名前を伺うことがなくなるので、取り次ぎがスムーズになります。
用件を伝える
担当者に取り次いでもらったら用件を伝えます。
『いつもお世話になっております。株式会社○○の○○と申します。ただいま、お時間をいただいてもよろしいでしょうか。』
また、話が長くなるときは、下記のように所要時間を伝えるのが一般的です。
『先日ご提案させていただいた件でご連絡させていただきましたが、10分ほどお時間を頂戴することが可能でしょうか。』
担当者の中には忙しい方もいるため、話が長くなる電話は話し終えるまでに必要な時間を伝えると相手にも迷惑がかかりません。
もし、相手に時間がない場合、改めて機会を設けてもらうようにしましょう。
相手が不在のとき
相手が不在の場合は伝言を残す必要があります。
基本的には用件を伝えるのではなく、帰社時間を聞いて、こちら側から改めて電話をかけるようにしましょう。
しかし、重要度が低いときは、伝言で済ませるのも1つの手です。相手に電話の時間を確保させる必要がないため、負担も少なくなるでしょう。
担当者が不在のときは、帰社時間と再度電話をする旨を伝えます。
『○○様のお戻り時間はいつ頃になりそうでしょうか。そのお時間にこちらから改めてご連絡差し上げます。』
このときに電話を担当してくれた方の名前を聞いておくと安心です。
正しく電話を切る
用件が終了したら電話を切ります。
ビジネスにおいては、電話をかけた側から切るのがマナーです。そのため、こちら側から電話を切るようにしましょう。
ただし、電話の相手がクライアントのときは、相手が切るまで待つのが一般的です。
相手の立場に合わせて切り方を変えるようにしましょう。
また、電話を切るときは、静かに受話器を置くのが基本です。投げるように受話器を置くと、切断するときに雑音が大きくなります。
相手に不快感を与えてしまう可能性があるので、受話器を置くときは十分に注意しましょう。
新人が電話対応するときに気をつけるべきマニュアル

新人が電話対応をする場合もあるでしょう。新人は基本的なビジネスマナーを知らないことも多く、適切な指導が必要です。
ここでは、新人が電話対応するときに気をつけるべきマニュアルを紹介します。
保留ボタンを使用する
電話対応をする際、確認や取り次ぎが必要な場面もあるでしょう。
このとき、保留ボタンを使用することが大切です。
電話越しに社内の会話が聞こえたり、雑音が相手の耳に入ったりする可能性があります。
新人だと慣れていない可能性もあるので、気を付けましょう。
社員の名前に敬称はいらない
社外の人に自社の社員の名前を伝える際は、敬称を付ける必要はありません。
新人社員の場合、上司を「○○さん」「○○課長」と敬称付きで呼びがちですが、ビジネスシーンにおける電話対応では敬称を付けずに呼ぶのがマナーです。
正確に取り次ぎを行う
新人の場合、取次の際に社員や部署の名前を正確に把握できていない場合も多いでしょう。同姓の社員に間違って取り次いでしまうなどのミスもあります。
取り次ぎの際は、相手から取り次いで欲しい社員の名前や部署を正確に聞きましょう。そして、正確に取り次ぎを行うことが大切です。
クレーム対応するときの電話マニュアル

次は、クレームの電話対応マニュアルについて紹介します。
どのように対処すればいいのかわかるので、ぜひ参考にしてみてください。
状況の理解が非常に重要
クレームの電話対応においては、まず状況を理解することが非常に重要です。
特に相手が怒っているときは、こちら側から話をしてしまうと余計にヒートアップしてしまう可能性もあります。
まずは状況を確認して、相手が怒っている場合は話を聞くことに徹するのが基本です。
また、落ち着きを取り戻してから意見を言うようにしましょう。
クッショントークをうまく活用する
クッショントークとは、お詫びやお願い、反論などをする際、文章の前に「恐れ入りますが」などの特定の言葉を入れて話すことです。
これによって文章が柔らかくなるため、相手の気持ちに配慮しながら話せます。
クッショントークで使われる代表的な言葉は、下記の通りです。
- 「お手数をおかけしますが」
- 「あいにく」
- 「残念ながら」
- 「よろしければ」
- 「恐れ入りますが」
- 「失礼ですが」
- 「申し上げにくいのですが」
- 「差し支えないようでしたら」
- 「可能であれば」
- 「申し訳ありませんが」
クレームの電話対応は相手が怒っているときもあるので、クッショントークを使うことで相手を落ち着かせる効果も期待できるでしょう。
お詫びを申し上げる
会社側にミスなどがあった場合は、相手にお詫びをするのが一般的です。
『このたびはご迷惑をおかけしてしまい、深くお詫び申し上げます。』
しかし、こちら側に非がない場合に謝ってしまうと、知らないミスを認めてしまうことになります。そのため、安易に謝ってしまうのは適切な対応ではありません。
相手が怒っているときは、怒らせてしまったことに対して謝るようにしましょう。
そうすることで、ミスを認めずに相手の気持ちに配慮できます。
また、受付として電話を取るときに謝るのは避けるようにしましょう。担当者や関係者に取り次ぎをして、クレーム対応を任せるのが一般的です。
2次クレームを発生させないように気をつける
クレーム対応では相手が怒っているため、慎重に配慮することが求められます。
もし気に触ることをしてしまうと、2次クレームにつながる可能性があるので、十分に注意しましょう。例えば、たらい回しは避けるようにします。
電話対応の担当者を3回以上変えてしまうと、2次クレームを誘発させてしまう可能性があるかもしれません。
そのため、担当者の変更は2回までに留めておくのが好ましいです。
また、「待たせすぎてしまう」「話をさえぎる」「責任逃れをする」という行為も相手をヒートアップさせる原因になるので、気をつけましょう。
マナーや言葉遣いをおさらい!電話対応でやってはいけない3のこと

電話対応でやってはいけないことが主に3つあります。
確認することでマナーや言葉遣いをおさらいすることができるので、ぜひ確認するようにしてください。
「はいはい」という言葉を使う
受け答えをするときに、「はいはい」という言葉を使うのはマナー違反です。軽く聞き流している、自分のことをなめているというように思わせてしまいます。
返事をするときは、「はい」と1回だけ言うようにしましょう。
文のはじめに否定語を使わない
文のはじめに否定語を使うのはマナー違反です。「しかし」などの否定語を使うと、相手は自分のことを拒否していると思わせてしまうので、好ましくありません。
反論するときは、できるだけクッショントークを用いて柔らかく表現するのが好ましいです。
曖昧な表現は避ける
曖昧な表現はできるだけ避けるようにしましょう。
「たぶん」や「いわれています」というような言葉は、説得力が失われてしまうため、相手を不安な気持ちにしてしまいます。
しかし、電話対応においては、自分が把握していない内容を聞かれることも多いです。
そのときは、資料を確認したり、上司に聞いたりして正確な情報を適切に伝えるようにしましょう。
電話対応マニュアルの作り方

電話対応マニュアルを作っておくと、電話対応の質が上がり、トラブルなどが少なくなります。ただ、電話対応出に慣れていない新人などは、マニュアルがあっても使いこなせないかもしれません。
そのため、以下のポイントに気を付けて電話対応マニュアルを作成すると良いでしょう。
- よくある対応や質問がすぐ分かるマニュアルを作成する
- 頻出のフレーズやトークスクリプトをまとめる
- エスカレーション先を明確化する
よくある対応や質問がすぐ分かるマニュアルを作成する
電話対応マニュアルを作成する際は、よくある対応や質問がすぐ分かるようにしましょう。
電話対応マニュアル内に検索機能を作ったり、Q&Aのページを用意するのがおすすめです。必要な情報をすぐ見つけられる電話対応マニュアルが理想です。
電話対応中は、マニュアルを細かく確認するのが難しいかもしれません。特に電話対応が苦手な人や新人はそれが顕著です。
電話対応でトラブルを起こさないようによくある対応や質問がすぐ分かるマニュアルを作成することをおすすめします。
頻出のフレーズやトークスクリプトをまとめる
電話対応マニュアルを作成する際は、頻出のフレーズやトークスクリプトをまとめておくようにしましょう。トークスクリプトは、電話対応の「台本」のようなもののことを言います。
電話の出方から、相手からの質問とその対応、電話の流れを台本としてまとめるのがおすすめです。
トークスクリプトは会話のパターンごとに作成しましょう。
また、電話対応ではマニュアル通りにいかないこともあるため、困ったときのフレーズを用意しておくと良いです。
以下のように、クッション言葉を使用したフレーズをマニュアル化しましょう。
【相手の名前や社名が聞き取れなかったとき】
- 「恐れ入りますがもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。」
- 「申し訳ございません。お声が遠いようなので、もう一度お願いいたします」
【担当者が不在のとき】
- 「申し訳ございません。○○は現在外出中です。」
- 「私でよろしければご用件をお伺いいたします」
- 「伝言等ございましたらお伝えいたしますが、いかがいたしますか。」
【すぐには回答できないとき】
- 「申し訳ございません。確認にお時間をいただきたいので、後ほど折り返しでご連絡させていただいてもよろしいでしょうか。」
- 「ただいま確認いたしますので、少々お待ちいただけると幸いです。」
エスカレーション先を明確化する
電話対応マニュアルでは、内容や状況ごとのエスカレーション先を明確化しましょう。エスカレーションとは、担当者や上司に対応を取り次ぐを言います。
エスカレーションするようなときは、一次対応ではどうにもならなくて、専門職やベテランに取り次がなければならないような状況です。トラブルが深刻になったり、顧客を怒らせたりしないようにするためには、ここでの対応が重要です。
クッション言葉を用いて相手に誠実な対応を行い、迅速にエスカレーションしましょう。確認に時間を要する場合は、その旨を理由とともに伝え、折り返しの約束をします。
自社で対応することが難しいなら代行会社を利用するのがおすすめ

企業の中には、電話対応業務に対して大きな負担を感じているところもあるのではないでしょうか。
自社で電話対応を行う場合、マナーや言葉遣いに注意しなければならないため、マニュアルの作成が必要です。また、適切な電話対応をさせるために、教育なども必要になるでしょう。
コア業務もある中でそれを行う必要があるため、自社では到底対応しきれないケースもあるかもしれません。
自社で対応が難しいと感じる方は、電話対応をアウトソーシングできる代行会社の利用がおすすめです。
代行会社にアウトソーシングすることで電話対応をする必要がなくなるため、企業は下記のようなメリットが得られます。
- 人件費や教育コストの削減
- 営業時間外の対応が可能
- 災害時の機能不全を防げる
電話対応業務の委託や代行会社に興味がある方は、下記の記事がおすすめです。
アウトソーシングの概要だけでなく、選び方やおすすめの代行会社も紹介しているので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。
まとめ
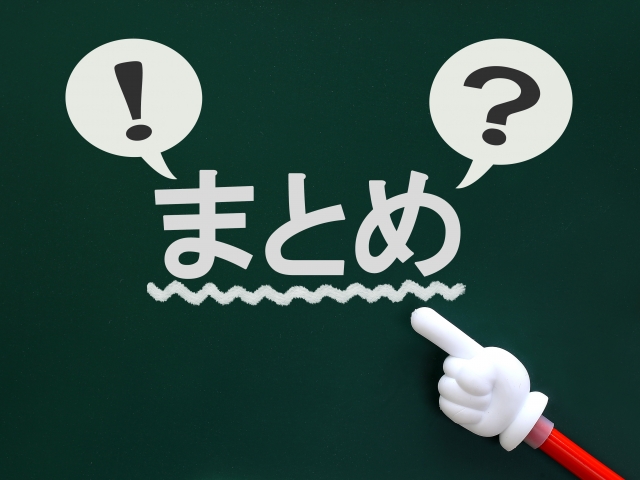
今回は、電話対応マニュアルについて詳しく紹介しました。
電話対応はその企業の代表として受け答えをするため、正確な言葉遣いとマナーが求められます。
適切に対応できないとクライアントに不快感を与える心配もあるため、マニュアルを作成して正しく受け答えができる体制を構築することが重要です。
電話対応業務まで自社で行うのは難しいと感じている担当者の方は、代行会社の利用がおすすめです。
コスト削減などさまざまなメリットを獲得できるので、興味のある方はぜひ利用を検討してみてください。