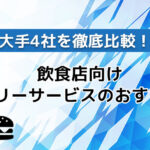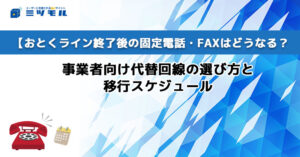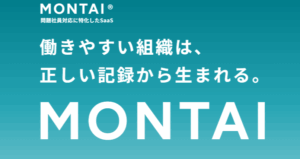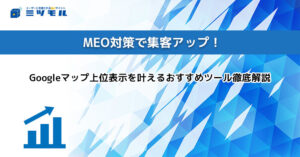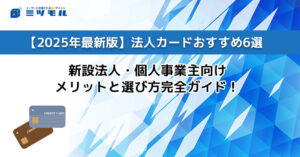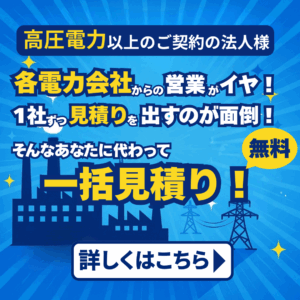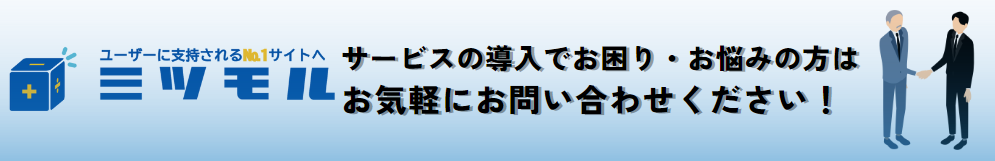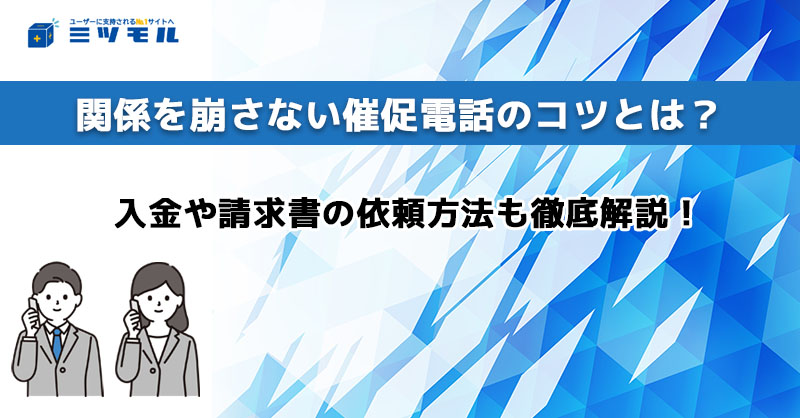
催促電話は、取引先にかける電話の中でもデリケートな内容です。
しかしビジネスにおいて相手に催促をしなければならない場面は避けて通れません。
催促の仕方を間違えると、大切な取引先との関係性を損なってしまう恐れがあります。
特に電話での催促は、相手の感情や状況が見えにくいため、慎重なアプローチが必要です。
本記事では相手に不快感を与えず、円滑に催促できる電話のコツを徹底解説します。
催促電話をしなければならない状況の方にはすぐに実践できる会話文もご紹介します。
催促電話の仕方を知識として身につけたいという方もぜひ参考にしてください。
目次
催促電話の目的とは?
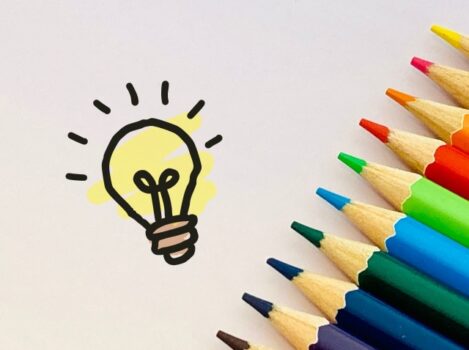
催促電話の最大の目的は、支払いが遅延している事項を相手に確認し、適切な対応を促すことです。
ビジネスにおいては、取引先との信頼関係を維持しつつ円滑に業務を進める事が重要となります。
また催促を単なる「強要」と捉えられないよう配慮し、相手に不快感やストレスを与えずに問題解決へと導くことも重要なポイントです。
適切なタイミングと言葉を選ぶことで相手との信頼関係が悪化せず良好な関係を保つことができるでしょう。
催促電話前に確認すべき3つの注意点

催促電話をかけるとき、電話の前に確認すべき注意点として3つ挙げられます。
- 催促電話の時間は最適なタイミングか
- これまでの過去の対応履歴をチェックしているか
- 相手から問い合わせが来ていないか
3つの注意点について、詳しくみていきましょう。
催促電話の時間は最適なタイミングか
催促電話は、相手の業務や生活リズムを考慮したタイミングで行うことが重要です。
時間やタイミングのポイントは以下の通りです。
- 相手企業の就業時間内に電話をする
- 入金の催促時は最速から翌営業日くらいまで待つ
例えば、始業直後や昼休み直前・終業間際は避け、相手が比較的落ち着いて対応できる時間帯を選びましょう。
相手が多忙な時間に電話すると、内容を十分に伝えることができず、印象を悪くしてしまう可能性があります。
催促電話を行った後もゆとりをもって待つことも今後の関係性を維持するポイントとなるでしょう。
これまでの過去の対応履歴をチェックしているか
催促電話の前には、必ずこれまでの連絡記録や対応履歴を確認しましょう。
依頼方法によっては正しく届いていないもしくは正確に伝わっていない可能性があります。
なかには自社側のミスである可能性も考えられます。
確認をせずに催促電話をかけると、相手企業との関係悪化にも繋がるかもしれません。
確認する主な事項は以下の通りです。
- メールと郵送のどちらで依頼していたか
- どこに依頼を送っていたか(アドレスや住所など)
- 記載漏れや記載内容に誤りはないか
- 相手が分かるように確実に依頼できているか
過去にどのような経緯でやり取りが行われ、どのような約束や期限が設定されたのかを把握しておくことで、
慌てずに冷静に受け答えができます。
また相手からの反応や対応のスピード、以前の支払い状況の傾向なども確認することで、より適切な伝え方や提案が可能になります。
過去の履歴を踏まえた対応は相手に「状況を理解してくれている」という配慮が伝わりやすく、交渉や依頼がスムーズに進みやすくなります。
相手から問い合わせが来ていないか
催促電話をかける前に、相手からすでに問い合わせや連絡が入っていないかを確認することも非常に重要です。
メール、FAX、郵送での通知など複数の連絡手段で見落としている可能性があります。
不要な催促電話を避けるためにはまず自社をチェックすることで、不信感や関係悪化の防止にもなります。
より的確で無駄のないスムーズな業務を実現するために事前に確認しておきましょう。
催促電話をするのはどんな時?必要なシーンをご紹介

ここでは催促電話をするときはどんな時かご紹介します。催促電話はとてもデリケートな内容になります。
そのため"催促電話をしてもよいのか"、"どんな場合に催促電話をしたらいいのか"不安に思う方も少なくありません。
催促電話を行うシーンは以下の通りです。
- 期日後も未入金のケース
- 継続的に未払いが発生しているケース
それぞれ詳しくみていきましょう。
期日後も未入金のケース
催促電話が最も必要となるのは、支払期日を過ぎても入金が確認できない場合です。
このようなケースでは取引先との信頼関係を維持しながらも、確実に回収を図る必要があります。
メールや郵送での催促が先に行われるケースもありますが、相手が見落としている可能性や、緊急性が伝わりにくいこともあるため、電話で直接確認することが有効になります。
催促電話では単なる「入金のお願い」ではなく、相手の事情を丁寧にヒアリングし、支払い意思の確認や今後の対応方針を明確にすることが大切です。
また催促電話の場合はトラブルを防ぐために記録を残すことが必須です。
通話内容、相手の回答、約束した支払日などを文書化し、必要に応じてメールでも確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
通話の中で支払期日を約束した場合は期日の前日に一度確認の連絡をしておくとスムーズに入金まで進むことができるでしょう。
また催促電話で非常に重要なのは感情的にならないことです。これはビジネスマナーとして冷静かつ丁寧な口調で会話をすることが重要なポイントになります。
信頼関係の維持を保つためにも意識して対応しましょう。
継続的に未払いが発生しているケース
同じ取引先から繰り返し未払いが発生している場合、早急な対応が必要です。
1回のみ支払いが遅れたケースでは一時的な事情と判断することもありますが、繰り返し未払いが発生している場合、異なるアプローチをすることが重要となります。
継続的に未払いが発生している場合は相手企業の資金繰りや経営困難も考えられます。
催促電話で単に入金のお願いをするだけでなく根本的な原因をヒアリングする必要があります。
また取引継続の可否についても検討が必要です。催促電話の際に、今後の取引条件について率直に話し合うことで、お互いにとって持続可能な関係を築くことができます。
催促の記録は詳細に残し、対応履歴を社内で共有しておくこともポイントになります。
ビジネスマナーを押さえた催促電話の3つのポイント

上記では催促電話が必要なシーンをご紹介しました。
そのうえでビジネスマナーを配慮しながら催促電話を行う3つのポイントをご紹介します。
ポイント1 第一声のトーンは明るく聞き取りやすい声で話す
催促電話をかけるときは、第一声のトーンや話し方を意識しましょう。
電話する際、顔が見えないのが特徴です。そのため声の印象が非常に重要となります。
電話の第一声は相手にいい印象を与えられるよう、明るく聞き取りやすい声で話すことを心がけることも大事なポイントです。また相手が応答した場合、社名と自分の名前を名乗ることも必須です。
社名と自分の名前を名乗った後には一文を付け加えて、相手の都合を聞き電話の要件を伝えるとより気遣う印象も与えることができるでしょう。
ポイント2 一方的に責めるような言葉や話し方はNG!
催促電話というデリケートな内容だからこそ、内容の伝え方には配慮する必要があります。
感情的になって相手を責める口調になってしまうことは避けましょう。
ビジネスマナーを意識しながら丁寧な口調を心掛け、相手の立場を尊重することも今後の関係を維持していくうえで大事なポイントになります。
また話すスピードも電話の際は非常に重要です。
早口で威圧的な話し方ではなく、相手が聞きやすい落ち着いたトーンで話すこともビジネスマナーとして意識しましょう。
相手が前向きに対応してくれるような行動をすることで信頼関係を築くことが可能になります。
ポイント3 クッション言葉を取り入れる
催促電話をかける際は、クッション言葉を使うのも非常に有効です。
クッション言葉を取り入れてから用件を伝えることで、相手の立場を尊重していることが伝わりやすいでしょう。
クッション言葉としてビジネスで利用されるフレーズは次で詳しくご紹介します。
ただしクッション言葉を多用しすぎることは避けましょう。
クッション言葉は適切な場面で適切なフレーズを使用することで相手へ不快感を与えず、円滑に用件が進みやすくなります。
催促電話で使える会話例文やフレーズ集

ここでは催促電話の時に使用できるフレーズをご紹介していきます。
さらにすぐに実践できる会話の例文もご紹介します。
会話の例文については以下の3つのシーンを例として挙げました。
- 支払いや未入金催促の場合
- 見積もりや請求書催促の場合
- その他の場合
催促電話でどのように内容を伝えたらいいか分からないと不安な方は必見です!
相手に不快感を与えないフレーズとは?
催促電話において、相手に不快感を与えずに要件を伝えるためには、適切なフレーズ選びが欠かせません。
重要なのは相手の立場を配慮しつつ、要件を丁寧に伝えることです。
一般的にクッション言葉とも解釈され、主にビジネス場面で使用されるフレーズは以下の通りです。
- お忙しいところ恐れ入りますが~
- ご多忙中と存じますが~
- ご検討いただいているところと存じますが~
- 急かすようで大変恐縮ですが~
- たびたびのご連絡となり恐れ入りますが~
上記の一文を電話の最初に使用することで相手に不快感を与えず配慮している印象を与えます。
パターン1.未入金催促の場合
未入金の場面では、催促電話の中でもデリケートな内容に入ります。
そのため丁寧な言葉遣いを意識して相手の気分を害さないようにしましょう。
例文①
お忙しいところ恐れ入ります。
【会社名】の【名前】と申します。
この度は【商品名/サービス名】のご購入、ありがとうございました。
本日は【商品名/サービス名】の入金確認ができておらず、お電話させていただきました。
行き違いのご連絡でしたら申し訳ありません。
恐れ入りますが、【商品名/サービス名】の入金日を教えていただけますでしょうか。
例文②
お忙しいところ恐れ入ります。
【会社名】の【名前】と申します。
この度は【商品名/サービス名】のご購入、ありがとうございました。
先日お送りした請求書について、入金確認ができておらず、請求書が届いてないのではないかと思いご連絡させていただきました。
行き違いのご連絡でしたら申し訳ありません。
○月○日の〇時頃にメールにてお送りさせていただいておりますが、貴社のもとに届いておりますでしょうか。
ご多忙中と存じますが、ご確認いただけますと幸いです。
パターン2.見積もりや請求書催促の場合
こちらのパターンは見積もりを依頼し、まだ手元に確認できていない場合や請求書がまだ届いていないケースの例文になります。
見積もりや請求書催促は、会計処理や契約を進める上で必要な書類です。
催促時は届いていない旨をただ伝えるだけではなく、支払いが遅れてしまう可能性なども含めて確認しましょう。
例文①
いつもお世話になっております。
【会社名】の【名前】と申します。
お忙しいところ恐れ入ります、○月分の請求書につきまして弊社の方で到着が確認できておりません。
請求書の到着が遅れてしまいますと、ご入金が遅くなってしまいます。
行き違いのご連絡であれば大変申し訳ないのですが、一度ご確認いただけますでしょうか。
例文②
いつもお世話になっております。
【会社名】の【名前】と申します。
先日は貴社の【商品名/サービス名】のご案内ありがとうございました。
本日は【商品名/サービス名】のお見積もりの到着が確認できておらず、お電話差し上げました。
行き違いのご連絡でしたら申し訳ありません。
お手数をおかけしますが、貴社とのお取引をスムーズに進めるためにも、一度ご送付いただいているかご確認いただけますでしょうか。
パターン3.その他の場合
取引先に案件を依頼する場合や打ち合わせをお願いする場合にも、催促電話が必要な場合があります。
入金や請求書催促に比べれば催促しやすいものの、相手の気分を害さないように注意が必要です。
例文①
いつもお世話になっております。
【会社名】の【名前】と申します。
○月○日に、【案件名】のご依頼をメールにてお送りいたしましたが、ご返信が確認できておらずご連絡させていただきました。
うまくメールが届いていない可能性もあるのですが、内容はご確認いただけておりますでしょうか。
例文②
いつもお世話になっております。
【会社名】の【名前】と申します。
○月○日にお打ち合わせをご依頼させていただきましたが、ご都合はいかがでしょうか。
スケジュールが難しければ別日にて調整いたしますので、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。
相手が対応した際のお礼方法とは?

催促電話を行った後、相手が入金や支払いに関して対応した場合には、
必ず感謝の言葉を伝えることがビジネスマナーとして重要です。
催促電話を行った側の視点では本来の入金義務を果たしただけという意見もありますが、
「対応してくれたこと」に対する丁寧なお礼は、今後の良好な関係維持に大きく影響するといえるでしょう。
継続的に取引がある場合には、「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」といった表現を利用するのも最適といえます。
些細な事でも感謝の言葉を伝えることはビジネスにおいて大事なポイントです。
催促電話に関するよくあるQ&A

催促電話に関して調査する中で、以下2つの疑問を抱いている方が多く見られました。
- 相手が不在の場合は?
- メールで催促してもよい?
2つの疑問について、詳しくみていきましょう。
相手が不在の場合は?
催促電話をかけたものの、相手が会議や休みなどの理由で離席しているケースは多いです。
その場合は、日付や時間を改めて自分からかけ直すようにしましょう。
可能であれば相手のスケジュールを確認しておくことで、何度も電話をかける手間がなくなります。
また相手からかけ直すことを提案されるケースもありますが、
相手がかけ直す時間などが明確ではない場合は、できる限り自分から日にちや時間を改めてかけ直す方が確実でしょう。
催促電話をした際に、電話を受けた方が伝言や要件を伺う場面も考えられます。
その際は相手担当者のことを考え、契約関連の担当者以外の方に伝えるべきではありません。
重要事項だと伝わるように簡単な内容を伝え、メインの内容に関しては直接担当者のみに伝えるとより担当者との信頼関係を築くことが可能になります。
メールで催促してもよい?
メールでの催促が適しているかは、内容や要件によって大きく変わります。
例えば、期日まで数日しかないような要件をメールで伝えるのはNGです。
メールを確認するタイミングは人それぞれなので、場合によっては期日当日に相手担当者がメールを確認する可能性も考えられます。
反対に急ぎの内容でない場合は、一度メールで促すことも選択肢のひとつです。
例えば、出欠関連の催促はメールで行うのが良いでしょう。文章として内容を残しておくことで、催促電話をかける際にも要件がスムーズに伝わりやすくなります。
電話で催促する必要があるか、メールで確認する事項なのかタイミングや重要性を判断し、臨機応変に対応することがポイントです。
まとめ
今回の記事では催促電話のコツや注意点について解説しました。
催促電話は、支払いに関するデリケートな問題を扱うため、相手との関係性に大きな影響を及ぼします。
適切なタイミングや言葉遣いを意識しながら、ビジネスマナーを踏まえて丁寧に対応することを心掛けると、信頼関係を損なわずに円滑な回収が可能になるでしょう。
今後の関係性もより良好な関係を構築するために、相手が対応した際には、感謝の言葉をしっかり伝えることも欠かせません。
催促電話は単なる業務連絡ではなく、ビジネスにおける信頼とマナーが問われる場面と考えられます。
本記事でご紹介したポイントやすぐに実践できる会話例文をぜひ参考にしてみてください!