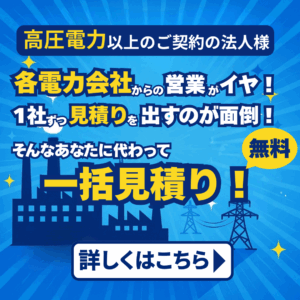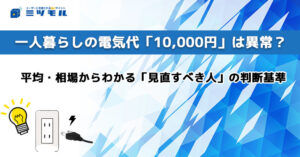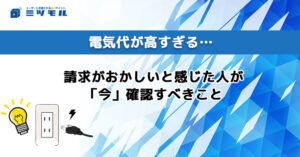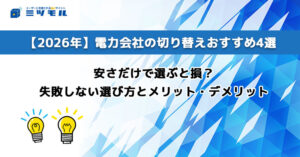企業を経営していくうえで、自然災害やサイバー攻撃といった予測ができない事態が起こりうるリスクは
避けられません。
こうしたリスクに直面した際、BCP対策は重要となってきます。
「BCP対策ってなに?」
と思っている方もいるでしょう。
事業を停止せずに継続させるための仕組みが「BCP対策(事業継続計画)」です。
BCP対策は法人において信頼性やブランド力を左右する重要な課題となっています。
本記事ではBCP対策の目的と重要性、防災対策やBCMの違いから運用のポイントまで徹底解説します!
規模の大きい企業から中小企業まで起こりうるリスクのため、現在BCP対策を検討している方は必見です!
\まずは無料でご相談!/
目次
BCP対策(事業継続計画)とは?

BCP対策とは地震や台風などの自然災害やサイバー攻撃、大規模な感染症の流行といった問題発生時に、事業を継続または復旧する為の仕組みや行動計画を整備することを指します。
英語の「Business Continuity Plan」の頭文字を取って、BCPと呼ばれています。
「Business Continuity Plan」を日本語に訳すと、事業継続計画を意味します。
問題が発生した後のことを事前に想定し、早期継続・復旧ができる計画を立てておくことが、BCP対策です。
近年たびたび発生している大震災などの自然災害や感染性ウイルスの流行などで、BCPを策定しているかどうかが事業の復旧率に大きな差が出るといっても過言ではありません。
そのため下記のようなBCP対策を支援する、"BCP対策ソリューション"を導入する企業が増えています。
主なBCP対策ソリューションは以下の通りです。
- 復旧のためのデータバックアップやデータレプリケーション
- 災害時の社員の安否確認
- 自宅からでも仕事ができる環境を提供するリモートアクセス
これらは企業価値向上にも直結するため、BCP対策は経営リスク管理の中核として急速に重要性が高まっています。
BCPが注目されている背景
BCPが注目されている背景には、複数の要因があげられます。
BCP対策をする目的は?
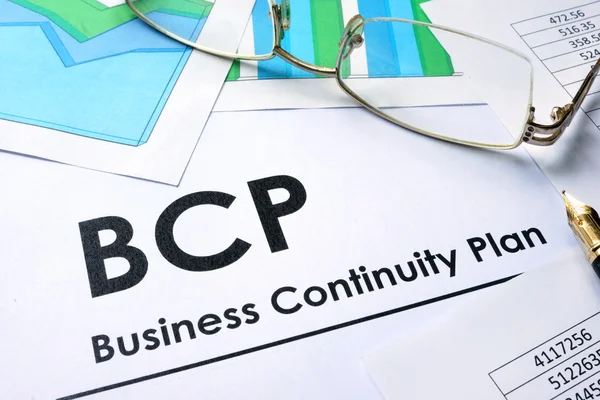
緊急事態が発生した際に、企業が事業を継続するための重要な経営戦略といえるでしょう。
予期せぬ事態が発生した場合でも対策をしっかりしていることで、その影響を最小限に食い止めることが可能です。
もう一つの重要な目的は、緊急事態発生後の復旧を可能な限り早める事です。
緊急事態下では、何から手をつけるべきか混乱してしまう企業も少なくありません。
BCP対策は単に業務を守るだけでなく、従業員の安全と安心を確保する役割も果たします。
大規模災害や感染症拡大時には、まず社員の安否確認を迅速に行い、適切な行動指示を出せる体制が不可欠です。
従業員が安全な状態にあることを確認したのち、企業は事業の復旧作業などの次のステップに進むことができます。
\まずは無料でご相談!/
セルフチェックリスト診断
BCP対策を始めるにあたり、現状の備えがどのくらいかを確認するためのセルフチェックリストを作成しました。
以下の10項目について、自社の状況をチェックしてみてください。
☑ 自社の重要業務(止められない業務)を把握し優先順位をつけているか
☑ 地震・水害・感染症・サイバー攻撃などリスクごとの影響度を把握しているか
☑ 災害時に備えた代替拠点や代替手段を用意しているか?
☑ 復旧目標時間(RTO)や許容データ損失時間(RPO)を数値で設定しているか
☑ 従業員の安否確認手段(システムや連絡網)を整備しているか
☑ 緊急時の指揮命令系統(誰が意思決定するか)を明確化しているか
☑ 主要取引先や仕入先のサプライチェーンリスクを把握しているか
☑ 社員に対し年1回以上の教育を行っているか
☑ BCPを年1回以上見直し、最新化しているか
☑ 取引先や金融機関へ BCPの存在を提示し信頼獲得に活用しているか
【診断基準】
8個以上当てはまる ⇒ BCP対策は比較的しっかり整備されている状況
5〜7個当てはまる ⇒一定の備えはあるが、改善の余地あり
4個以下 ⇒BCP対策が不十分。早急に整備を進める必要あり
\まずは無料でご相談!/
BCP対策のメリットは?

BCP策定のメリットは、大きく分けると3つあげることができます。
なぜ大切なのかを理解するためにもチェックしておきたい重要なポイントになります。
- 被害を最小限に抑えることができる
- 信用できる会社として認識してもらえる
- 補助金や助成金の対象になる
上記3点について詳しく解説していきます。
被害を最小限に抑えることができる
1つ目のメリットは万が一、自然災害やサイバー攻撃などの緊急事態が発生した際、企業への被害を最小限に抑えられる点です。
具体的には災害やシステム障害などによって事業活動が停止する事態を未然に防ぎ、仮に停止した場合も主要な事業だけでも早期に再開できる体制を構築できます。
これにより顧客へのサービス供給が途絶えることを回避し、売上の減少や市場シェアの低下といった経済的損失を大幅に軽減することが可能です。
さらに、BCPには従業員の安否確認や行動マニュアルも含まれるため、人命に関わるリスクも最小化し、社員の安全を守ることにも繋がります。
事業停止による連鎖的な被害を防ぎ、企業の存続そのものを守るための、極めて重要な取り組みと言えます。
信用できる会社として評価される
2つ目の重要なメリットは、BCPを策定することで信頼できる会社と評価されやすくなる点です。
BCP対策を実施している企業は取引先や金融機関などから「信頼できる会社」として高く評価されます。
近年では大手企業や自治体との取引において「BCP策定の有無」を確認されるケースが増えています。
同業他社と競合した際に、BCPを整備している企業は「緊急時にも取引が続けられる」「安心して契約できる」と判断され、受注や契約獲得の面で有利になりやすい傾向もあります。
従業員からも「安心して働ける会社」として評価されやすく、人材の定着や採用力の強化にもつながるでしょう。
補助金や助成金の対象になる
補助金や助成金は、国が行っているものから各地方自治体が行っているものまで様々です。
中小企業庁や地方自治体が、BCP策定を支援するための様々な補助金や助成金制度を提供しています。
設備投資やシステム導入、備蓄品の確保といったBCP関連のコストを軽減でき、
経営への負担を抑えつつ効果的な備えを実現できるため、
BCP策定をためらっていた企業にとっても前向きに進めることが可能になります。
ただし制度ごとに要件や申請期間が定められているため、事前に情報収集を行い、自社が対象となるか確認することが重要です。
\まずは無料でご相談!/
BCP対策を運用する注意点
BCP対策をするうえで注意点もあります。
注意点は主に2つ挙げられます。
- BCP策定にコストがかかる
- BCP通りに計画が進まない場合がある
2点について詳しくみていきましょう。
BCP策定にコストがかかる
BCP対策を導入する際の大きな課題のひとつとして、コストがあげられます。
人件費、コンサルティング費用、時間などBCPを策定するうえでマニュアルのみでは不十分といえます。
例えばデータのバックアップ環境を整えるにはクラウド利用料やサーバー費用が発生します。
さらに非常用電源や衛星電話などのインフラ設備も導入コストがかかります。
また定期的な訓練や見直しには人的リソースが必要となり、中小企業にとっては負担に感じられる場合も少なくありません。
段階的な導入や優先順位を明確にし、自社の規模や状況に合わせて国や自治体の補助金や助成金を活用しながら効率的に導入しましょう。
BCP通りに計画が進まない場合がある
BCPはあくまで「想定」に基づいて作成されるため、実際の緊急事態では計画通りに進まないことがあります。
想定を超える規模の災害により、代替手段が使用できない状況も生じる可能性があります。
またシステム障害やサイバー攻撃では、攻撃の手口が進化しているため、過去の対策だけでは対応できない可能性もあります。
実際の運用では想定外の事態にどう対応するかを社内で議論し、計画を改善し続ける仕組みが求められます。
さらに実践的なシミュレーションを取り入れることでより従業員の理解も深まるでしょう。
BCP対策の重要性とは?

ここではBCP対策の重要性を詳しく解説します。
BCP対策がないとどうなってしまうのか、一言で表すと「BCP対策をしなかったことで会社をたたまなければいけなくなる」ケースもあるということです。
現在、業種によってはBCP対策が義務づけられている企業も存在します。
非常事態への対策がない場合、取引先や顧客、従業員にも大きく影響します。
事業の縮小を余儀なくされたり、取引先との関係が終了するケース、
復旧に想定外の時間がかかり閉業せざるを得ないケースも挙げられます。
緊急時に事業を止めない又は迅速に復旧するためにあらかじめ仕組みを整えていきましょう。
義務づけられている業種をご紹介!
ここではBCP対策が義務づけられている業種について主な4つをご紹介します。
金融機関(銀行・証券・保険など)
金融機関は大規模災害が発生した場合でも決済システムを維持し、国民の金融取引を支える重要な役割を担っています。
時期は2000年代初頭から、金融庁の監督指針等によりBCP策定が事実上義務付けられてきました。
これによりシステムダウンや支店閉店といった事態にも早急に復旧できる体制が構築されています。
ライフライン事業(電気・ガス・水道)
電気・ガス・水道といったライフライン事業者は、国民生活と経済活動の基盤を支えるため、
災害時にもサービス供給を維持することが不可欠です。
2011年の東日本大震災以降、国土強靭化計画の一環として、各事業者にBCP策定の義務付けが進みました。
医療機関(特定機能病院・災害拠点病院)
2013年頃から特定機能病院や災害拠点病院は、大規模災害時に多数の傷病者を受け入れ、医療を提供し続ける使命を負っています。
これらの医療機関は、災害医療体制の強化の一環として、BCP策定が義務付けられました。
災害発生時でも医療従事者の確保や医薬品の供給を続け、救命活動を最優先に行うことができるようになっています。
介護保険事業所
2024年4月1日より、全ての介護保険事業所に対し、BCP策定と訓練の実施が義務化されました。
これは大規模災害や感染症パンデミックが発生した際にも、高齢者や要介護者の命と健康を守るため、
途切れなくサービスを提供し続けることを目的としています。
この義務化は、利用者の安全確保と事業所自身の持続可能性を高めるための重要な施策ともいえるでしょう。
\まずは無料でご相談!/
BCP対策をしていないことで起こりうるリスク
BCPを策定していないことで発生するリスクについて2つ解説します。
主にBCP対策していないと以下のことが発生する可能性があります。
- 取引先との契約がストップする
- 従業員の安全確保ができない
取引先との契約がストップする
BCPを策定していない企業は緊急時の事業継続力が不透明なため、
取引先から「供給が止まるリスクが高い」と判断される恐れがあります。
特に規模が大きい企業や自治体はサプライチェーン全体の安定性を重視しており、
取引継続の前提としてBCPの有無を確認するケースが増えています。
BCP対策をしないことで競争力が低下するリスクも発生します。
そのためBCPの策定は必須ともいえるでしょう。
従業員の安全確保ができない
BCP対策が不十分な場合、緊急事態において従業員の安全を適切に確保できず、
企業の安全配慮義務違反として法的責任を問われるリスクがあります。
労働契約法では企業に従業員の安全確保義務が課されており、適切な避難計画や安否確認体制の不備は重大な過失とみなされる可能性があります。
また従業員の信頼を十分に得られず、人材の流出や採用困難を招くリスクもあります。
以上のことからBCP対策は今後の安全を守るために必ず策定していきましょう!
\まずは無料でご相談!/
BCP対策したら会社の評価が上がった!運用後の企業の事例

BCP対策の必要性をより実感してもらうために、具体的な事例を見ていきましょう。
①BCP対策により、壊滅被害から早急に復旧できたリサイクル業者の例
とあるリサイクル業者の例です。
東日本大震災で焼却施設が全壊し事業が中断。
しかしBCP対策を策定していたことにより、早急に復旧できた実例です。
BCP策定により緊急用の通信手段として衛星電話を設置していたことにより、処理施設の修理業者に速やかに連絡が取れ、
震災の翌日には修理業者が復旧の確認作業に取り掛かることができました。
電話やパソコンは5日後に復旧、産業廃棄物の収集運搬及び清掃業務、リサイクル業務は震災後約1週間で復旧、
その他の中間処理業務についても 約1か月で復旧し、早期に完全復旧を果たしました。
地震直後に、現場の従業員の提案で大型発電機をレ ンタルしたことで、早期の業務再開につながりました。
参照元:https://www.tokyo-cci.or.jp/survey/bcp/file/bcp_130314a.pdf
②BCP対策により、被害から早急に復旧できた電気製造業者の例
東日本大震災で施設や設備被害に見舞われ事業が中断。
しかし、BCP対策により早急に復旧することができた実例です。
震災発生からわずか12時間後に、BCPに基づきノートPCの生産拠点である他県のグループ会社に代替生産の委託を行い
わずか12日後に、デスクトップ・パソコンの代替生産を開始する事ができました。
事前に、「生産が出来なくなったら」という事を想定して代替生産の方法を策定していたため、スムーズに事業を再開する事が出来ました。
参照元:https://www.tokyo-cci.or.jp/survey/bcp/file/bcp_130314a.pdf
\まずは無料でご相談!/
BCPにおけるマニュアルの種類

BCPの対象となる緊急事態とは、主に以下のように分類されます。
そのため、マニュアルもそれぞれの非常事態用に細かく分類されている必要があるのです。
| fa-flash自然災害 | 大震災・水害・台風など |
| fa-user-secret外的要因 | 仕入れ先が倒産・サイバー攻撃など |
| fa-frown-o内的要因 | バイトテロ・不祥事による役員の退職など |
自然災害のBCP対策マニュアル
自然災害の場合、以下のような内容を記載します。
通常は、PCでマニュアルの保管を行う企業が多いのですが、停電に備え印刷して保管しておくと停電した時も安心です。
- 人命救助の方法
- 避難方法
- 安否を確認する方法と連絡先の確認
- 被害状況の確認
- 停止した事業を代替設備で復旧させる方法
外的要因のBCP対策マニュアル
外的要因の場合、以下のような内容を記載します。
仕入先が倒産した場合、仕入先の二重化や変更先リストを策定する必要があります。
サイバー攻撃を受けた場合、社員や顧客、株主などの利害関係者に説明責任が問われます。
その通知内容や方法を決めておかなければなりません。
- 社外への状況説明の手順、担当者の選定
- 代わりの仕入れ先リストを選定
- 代わりの機器・システムの使い方
- 安否を確認する方法と連絡先の確認
- 取引先企業の連絡先と連絡する優先順位を選定
- 事業データを復旧させる方法
内的要因のBCP対策マニュアル
内的要因の場合、以下のような内容を記載します。
内的要因で、経営陣がもっとも恐れているのが、バイトテロや従業員テロです。
バイトテロや従業員テロとは、主に飲食店などでアルバイトとして雇用されている店員が、お店で商品などを利用して、
いたずらを行うところをSNSや動画サイトへ投稿して炎上し、企業に教育面や衛生面などで大きな損失を出すことです。
最近では、「いいねがほしい」「少し有名になりたい」などの理由で正社員でも発生する事は少なくないので注意が必要です。
このような場合、発覚すれば多くのクレームが寄せられ、窓口の増加やクレーム用のスクリプトを準備するなどの対応が必要です。
- 専任担当者の選定
- 謝罪文の作成やテンプレートを準備
- あらゆるケース別のシナリオを想定
- プレスリリースの作成、記者会見開催の方法
- 取引先企業の連絡先と連絡する優先順位を策定
- 再発防止のためのマニュアル策定
- 対応に追われることを想定し、継続業務の優先順位策定
このように、さまざまな要因によって事業継続が難しくなるため、考えられるリスクを想定し、マニュアルの策定や対策を策定しておきましょう。
\まずは無料でご相談!/
BCP対策と防災対策の違いとは?

ここまででBCP対策の重要性を少しでも理解いただけたでしょうか?
ここからは、良く間違えられる「BCP対策」「防災対策」の違いを説明します。
詳しい違いは下記で解説します。
対象の要因
| BCP対策 | 自然災害やバイトテロなど、すべての非常事態が対象 |
| 防災対策 | 地震、水害、台風などの自然災害のみが対象 |
対象になる範囲
| BCP対策 | 自社も含め取引先なども対象なので共同で対策を練る事もある |
| 防災対策 | 自然災害から現物資産を守る目的の為、自社のみが対象 |
対象になる対策
| BCP対策 | 何らかの要因により資産が失われた際に予備として資産を戻すルートを確保したり、レンタルの計画をたてたり、 設備を手動で使うためのマニュアルを作成するなど、主に事後対策 |
| 防災対策 | 自然災害により、自社の資産が失われないように事前に対策を講じます。 |
BCP対策とBCMの違いとは?
 BCPとBCMにはどのような違いがあるのでしょうか。
BCPとBCMにはどのような違いがあるのでしょうか。
両者の性質を確認します。
・BCM
BCPと似た言葉として取り扱われることが多いですが、BCMとは事業継続計画についての策定、改善・運用までをトータルで考えるのがBCMです。日本語では事業継続マネジメントを指します。
「対策手段の運用プロセス」を検討・設計するためのプロセスを組むのがBCMです。
・BCP
緊急事態発生時、事業への影響を極小化し、いち早く復旧できるようにしておくための計画です。「事業継続計画」と訳され、特に事業を継続することに重きを置いたリスクマネジメントです。
BCP対策 初動~運用までの流れ
BCP対策と防災対策の違いも知ったことでBCP対策のイメージがついたと思います。
では、実際にどのような計画を練るのかまとめましたので紹介します。
| 1:初動対応 | 非常事態が発生した際に、被害を最小限にとどめるために行う最初の活動です。 自然災害の場合、お客さまや従業員の安全を第一に被害を拡大させないよう措置を行います。 事業所からの退避、応急手当や初期消火、警察・消防への通報、安否確認や被害状況の把握などを行います。 |
| 2:仮復旧対応 | できる限り速やかに顧客・協力会社と連絡を取り、安否・被害状況の把握結果を踏まえ、 中核事業がダメージを受けたと判断したうえで継続方針を立案し、その実施体制を確立します。 |
| 3:本復旧計画 | 仮復旧した状態から平常時の業務形態に戻す計画になります。 平常時と同じく、「建物の修復の完了」「電気水道などのライフラインの復旧」 |
| 4:保守運用 | 初動、仮復旧、本復旧の計画をうまく運用させるための計画になります。 例えば、緊急連絡先の更新や最新の避難通路、防災備蓄用品の買い替え、避難訓練などを行う必要があります。 |
\まずは無料でご相談!/
BCPの策定方法

BCP対策の策定には大きく分けて2種類の方法があります。
「コンサルタントに依頼する」「ガイドラインを参考にしながら自社で作る」
どちらが適しているのか、費用の相場感も交えて見ていきましょう。
外部コンサルタントや行政書士に依頼する
「BCP策定に時間は割けない!」という方は、
BCP専門コンサルタントや行政書士に依頼し、必要な項目は打合せを実施しながら策定する方法があります。
まずは、外部に依頼する際の「メリット・注意点」を紹介します。
- 正確で的確な BCP対策が策定できる
- 策定にかかる、人的リソースが大幅に削減される
- 策定にかかる時間が早い
- 依頼する為には、費用が発生する
それでは「BCPコンサルタント・行政書士」の特徴を紹介します。
BCPコンサルタントへ依頼する
最大の特徴は、システム面に強いという事です。
また費用がかかる分、手厚くアドバイスやそれに付随するサービスなどが充実している会社が多いです。
行政書士に依頼する
最大の特徴は、法務に強いという事です。
しかしシステム面ではそこまで強くないため行政書士に依頼する場合は社内でシステムに強い人材がいるとスムーズに策定できるでしょう。
一般的な費用は30万円~50万円ほどかかります。
\まずは無料でご相談!/
BCP対策の課題
 昨今、急速にBCP対策を策定する企業が増えてきましたが、BCP対策についてはまだまだ課題があります。
昨今、急速にBCP対策を策定する企業が増えてきましたが、BCP対策についてはまだまだ課題があります。
継続的な運用見直しを図る必要があるBCPですが、企業を取り巻く環境などは絶えず変化しています。
これらの環境を考慮して都度変化に対応していかなければ、実効性のあるBCPは策定できません。
発生しうるリスクそのものが変化していることをふまえ、
定期的にBCPの見直しを図り、実効性のある対策を検討していく必要があります。
大規模災害は無差別に企業を襲います。BCPが適切に更新されている企業は、事業継続性が高く市場からの信頼を得られます。
BCP対策の効果についてしっかりと理解し、積極的に取り組んでいくことが重要です。
\まずは無料でご相談!/
まとめ
最後に本記事の最終チェックリストを確認し、おさらいしましょう。
✔BCP対策とは事業継続計画化で重要業務を止めない又は早期復旧するための計画
✔BCMや防災対策とは異なり事業活動を守る視点を重要視した計画
取引先や金融機関などから策定を求められるケースも増加
✔BCP対策の目的やメリットを理解したうえで策定をする
✔注意点として、コストや事が発生した場合に想定通りに計画が進まない場合があるため柔軟な見直しや訓練が必要である
✔BCP対策をしないことで起こりうるリスクを理解しよう
✔BCP対策の運用までの流れを把握しておこう
本記事ではBCP対策の重要性やメリットを解説してきました。
BCP対策をすることで注意点もありますが、事業を継続させることや従業員の安全を守るためにもしっかり策定を行いましょう!
策定が完了し実践できるようになるまで、コストや時間を要しますが、大きな影響を最小化するためにも重要な任務です。
ぜひ導入してみてください。
\まずは無料でご相談!/