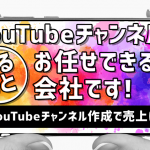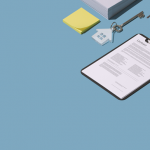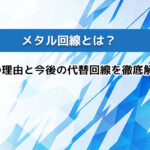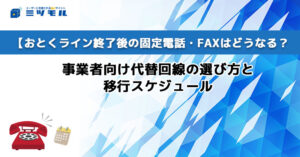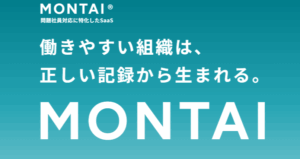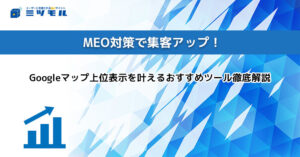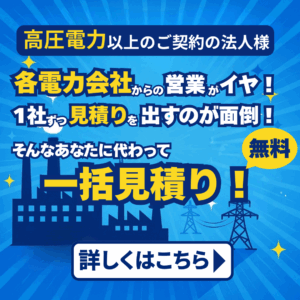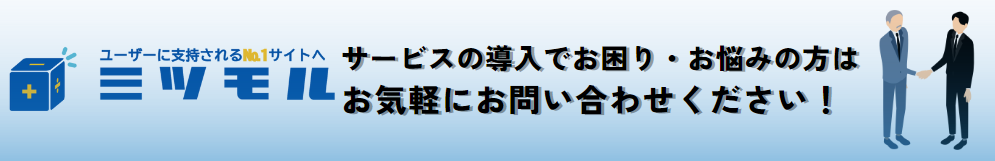近年ネットニュースが発達し、飲酒運転が原因の事故ニュースを毎日のように目にするようになりました。
アルコールチェッカーに対する需要も日々高まっています。
アルコールの影響は人それぞれ異なり、少量の飲酒でも基準値を超えてしまう可能性があります。そのため、自分の状態を客観的に確認できるアルコールチェッカーの活用がおすすめです。事前に測定することで、基準を超えていないかを判断し、うっかり違反を防ぐことができます。
本記事では、飲酒運転の基準や罰則の違いを詳しく解説するとともに、安全運転を守るための対策としてアルコールチェッカーの必要性についても紹介します。
飲酒運転を未然に防ぐために、ぜひ参考にしてください。
目次
飲酒運転とは

飲酒運転とは、お酒を飲んだ状態で車を運転することを指し、法律で禁止されている行為です。
2023年12月に施工された改正道路交通法により、一定台数以上の白ナンバー社用車使用している企業に対して、アルコールチェックが義務化されました。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、それぞれ基準や罰則が異なります。
酒気帯び運転は、血中アルコール濃度が0.3mg/ml以上または呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上の場合に該当し、違反として罰則が科されます。
一方で、酒酔い運転はアルコールの影響により正常な運転ができない状態を指し、飲酒量に関係なく、運転者の様子から判断されます。
例えば、まっすぐに歩けない、受け答えがはっきりできないなどの状態が見られる場合、酒酔い運転とみなされ、より重い罰則が適用されることがあります。お酒に弱くて少量の飲酒でも酔ってしまう方は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、それぞれ罰則が異なります。以下の表で違いを整理したうえで、詳しく解説していきます。
| 項目 | 酒気帯び運転 | 酒酔い運転 |
|---|---|---|
| 定義 | 呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上 | アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態 |
| 刑事罰 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 違反点数 | 0.15mg以上0.25mg未満:13点(免許停止90日) 0.25mg以上:25点(免許取り消し・2年間再取得不可) | 35点(免許取り消し・3年間再取得不可) |
| 同乗者の罰則 ※酒類提供者も同様 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 車両提供者の罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転は、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、違反点数はアルコール濃度によって異なります。飲酒運転の中では、一番軽い罪です。
前歴がない場合で90日間の免許停止処分、前歴があれば免許が取り消される可能性もあります。
計測数値が0.25mg以上の場合、処分内容に関しては0.15mg以上0.25mg未満の場合と変わりません。しかし、前歴にかかわらず一回の違反で免許取り消し処分になります。さらに、2年間は運転免許証の再取得ができない欠格期間です。
アルコールチェッカーの数値が0.15未満の場合は、罰則が科されたり、違反点数が加算されたりすることはありません。ただし、酒気帯び運転として注意されます。
酒酔い運転は、刑事罰として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、違反点数は35点(免許取り消し・3年間再取得不可)となります。
処分内容や違反点数を見ても、酒気帯び運転より重い罪だということがわかります。
また、酒気帯び運転ですら免停となるのに対し、酒酔い運転は更に10点も多く引かれてしまいます。免停はもちろんのこと、3年間は免許を取得することができません。
酒気帯び運転も決して軽い罪ではありませんが、それよりも重いのが特徴です。
飲酒運転の罰則を見ても分かる通り、少しでも飲んだら重罪となり、その後の生活にも影響が出ることがあるので注意しましょう。
さらに、飲酒運転は、運転者だけでなく同乗者や車を貸した人、酒を提供した人にも罰則があるため、関係者全員が責任を問われる行為です。
運転者に誘われて同乗した場合には同乗罪が成立しないこともありますが、飲酒運転の疑いがある運転手の誘いはしっかりと断ることが大切です。
また、酒類の提供の際にも車を運転する予定がないかを十分に確認するようにしましょう。
知っておきたいお酒の基礎知識

ここでは、覚えておきたいお酒の基礎知識について確認していきます。今回ご紹介する基礎知識は、以下の通りです。
- アルコール血中濃度と酔いの状態
- 飲酒運転の危険性|こんな時は運転をやめよう!
- 飲んだお酒は体の中でどうなる?
- 酔いが覚めるまでの時間とは?
どれもアルコールを飲む前に理解しておくと飲酒運転を防ぐことに繋がりますので、理解しておきましょう。
アルコール血中濃度と酔いの状態
アルコールの血中濃度と酔いの状態は、次の表のようになっています。
血中濃度(%) | 酒量 | 酔いの状態 | |
爽快期 | 0.02~0.04 | ビール中びん(~1本) 日本酒(~1合) ウイスキー・シングル(~2杯) |
|
ほろ酔い期 | 0.05~0.10 | ビール中びん(1~2本) 日本酒(1~2合) ウイスキー・シングル(3杯) |
|
酩酊初期 | 0.11~0.15 | ビール中びん(3本) 日本酒(3合) ウイスキー・ダブル(3杯) |
|
酩酊期 | 0.16~0.30 | ビール中びん(4~6本) 日本酒(4~6本) ウイスキー・ダブル(5杯) |
|
泥酔期 | 0.31~0.40 | ビール中びん(7~10本) 日本酒(7合~1升) ウイスキー・ボトル(1本) |
|
昏睡期 | 0.41~0.50 | ビール中びん(10本超) 日本酒(1升超) ウイスキー・ボトル(1本超) |
|
飲酒運転がもたらすリスクと現状
お酒に強い人や、普段から飲酒の習慣がある人は、「少しなら問題ない」と思い込み、飲酒後でも運転してしまう可能性があります。
しかし、どれほど飲み慣れていても、アルコールの影響を完全に避けることはできません。
アルコールは判断力を低下させ、反応速度を遅くするため、飲酒後の運転は非常に危険です。本人が大丈夫だと感じていても、適切な運転ができず、予期せぬ事故につながるリスクがあります。
飲酒運転がもたらすリスク
飲酒運転は、アルコールによって脳の働きが抑制され、正常な判断ができなくなることで発生します。その結果、
- 反応速度の低下(ブレーキが遅れる)
- 注意力の低下(周囲の状況を見落とす)
- 判断力の低下(危険な運転をしてしまう)
といった影響を及ぼし、交通事故を起こしやすくなります。
従業員が飲酒運転を起こすと、企業全体にも大きなダメージを与える可能性があるのです。
飲酒運転による事故の発生状況
| 飲酒の有無 | 交通事故件数 | 死亡事故件数 | 死亡事故率 |
|---|---|---|---|
| 飲酒なし | 282,072件 | 2,215件 | 0.79% |
| 飲酒あり | 2,346件 | 112件 | 4.77% |
| 合計 | 284,418件 | 2,327件 | 飲酒有は飲酒なしの約6.1倍! |
このデータからもわかるように、飲酒運転による事故は発生件数自体は少ないものの、死亡事故率が約4.77%と非常に高いことが特徴です。
これは、アルコールの影響で判断力が低下し、重大な事故につながりやすいためと言えます。
アルコールチェッカーの必要性とは

企業における飲酒運転防止の取り組みは、従業員の安全を守るだけでなく、企業の信頼にも大きく関わる重要な課題です。
飲酒運転は絶対に避けるべきですが、自分では気づかないうちに基準値を超えてしまっている可能性があります。特に、企業としては従業員が飲酒運転をしないよう管理する責任があります。
アルコールチェッカーを活用することで、適切な判断ができるようになります。
ここでは、アルコールチェッカーの必要性とその重要性について詳しく解説していきます。
なぜアルコール検知が必要なのか
企業にとって従業員の飲酒運転を防ぐことは、法的義務であるだけでなく、信頼を守るための重要な取り組み です。
特に、社用車を利用する業務では、飲酒運転が事故につながれば企業の責任が問われるだけでなく、社会的信用を失ってしまいます。
アルコールの分解速度は個人差が大きいため、自覚のない飲酒運転を防ぐためにも、アルコールチェッカーによる客観的な確認が重要になります。
アルコール検知を日常的に行うことで、従業員の意識向上にもつながり、安全な職場づくりにつながります。信頼される組織づくりのためにも、アルコールチェッカーを導入していきましょう。
運送業界・企業に義務付けられるアルコールチェック
飲酒運転撲滅のため、平成23年5月からアルコールチェックは義務化されています。
特に下記の事業者は必ずアルコールチェックが必要になりますので、まずは対象の事業者かどうか確認してください。
| 事業者名 | 詳細 |
一般旅客自動車運送事業者 | タクシー・路線バス・観光バスなど |
特定旅客自動車運送事業者 | 通勤通学用バス・施設の送迎バスなど |
一般貨物自動車運送事業者 | トラック・バンなど ※三輪以上の軽自動車や二輪は除く |
特定貨物自動車運送事業者 | トラックなど 特定1社のみの貨物輸送を行う事業者 |
貨物軽自動車運送事業者 | 軽トラック・軽バン・自動二輪など |
これらの主な事業者は、緑ナンバーや黒ナンバーになります。
そしてこれらの事業者に加えて、2022年10月より白ナンバー事業者に対してもアルコールチェックが義務化されることが発表されていました。
この道路交通法改正に関しては、警視庁から7月15日に当面の間白ナンバーの義務化を延期する旨が発表されましたが、義務化自体は近いうちに実施されることが決定している状況です。
白ナンバーとは主に事業所で使う社用車などにつけるナンバープレートで、具体的に義務化の対象となる白ナンバー事業者は、「乗用定員数が11人以上の自動車1台以上、または、その他の自動車5台以上を使用する事業者」となります。これらに該当する事業社に関しては「安全運転管理者」を決めて、15日以内に警察署に届け出る必要があります。
さらに、2023年12月から、「安全運転管理者」によるアルコール検知器を用いたチェックが義務化されました。
これらにより、運転の前後でアルコールチェックの実施と、記録の保存と検知器を管理する義務の2つの項目が追加され、企業の管理が今まで以上にしっかり求められるようになっています。
アルコールチェッカーを備え付ける
複数の営業所がある場合は、それぞれアルコールチェッカーを備え付ける必要があります。
また、遠隔地で業務を行う場合は運転手にアルコールチェッカーを携帯させてチェックを行いましょう。
点呼時にアルコールチェックを行う
業務の開始または終了時にアルコールチェックの実施を行いましょう。
点呼の際には運転手の顔色やアルコールの臭いがしないかの目視確認が重要です。
また、実際にアルコールチェッカーを使用して数値に問題がないかの確認も忘れずに行いましょう。
記録を1年間保持する
2023年12月の法改正により、アルコールチェックの記録を1年間保存する義務が新たに追加されました。
具体的には、運転前後のアルコール測定結果や確認内容を記録し、1年間保管する必要があります。
義務化対象外でもアルコールチェッカー導入がおすすめ

一般的にドライバーや運転手と呼ばれる方を雇っている企業では、アルコールのチェックが義務化されています。
しかし、現在ではそれ以外の義務化されていない業界でもアルコールチェックの実施が行われるケースが増えているのです。
理由としては下記の3点があげられます。
- コンプライアンスの遵守
- 社員の飲酒に対する意識向上
- 社員の健康管理
飲酒運転は、万が一業務中に事故を引き起こしてしまったら会社全体の責任問題にもなるなど、社会的信用を失う恐れもあります。
大きな社会問題となってしまった場合には会社自体の経営が困難になるケースもあるでしょう。
飲酒運転の罰則は昔に比べてとても重いものとなっておりますので、義務化されていない業界についてもアルコールチェックは検討したほうが安心です。
アルコールチェッカーを導入するメリットとしては、次のようなものがあります。
- 従業員を守る
- 運転手の意識が高められる
- 業務の負担を軽減できる
それぞれ解説していきます。
従業員を守る
アルコールチェッカーを導入することによって、従業員の飲酒運転を抑制できるメリットがあります。
アルコールチェッカーは目で見てわからない数値をしっかりと出してくれるため、万が一飲酒していたら運転をしないよう引き止めることが可能です。
特に多くの従業員を抱えている事業者は、一人ひとりの状態を細かくチェックすることは難しいでしょう。
しかし、アルコールチェッカーならデータ化ができるため、ひと目で飲酒の有無を確認できます。
これなら飲酒運転をして捕まってしまうことを防げるため、従業員が過ちを犯す心配もありません。
会社として従業員を守るためにも必要不可欠となっておりますので、飲酒運転一つで事業が台無しにならないためにも導入を検討しましょう。
運転手の意識が高められる
飲酒の有無を自己申告で行っている場合は、中には飲酒をしていてもしていないと虚偽の申告をする方もいるでしょう。
しかし、アルコールチェッカーを導入することでデータ化がされるため、虚偽の報告ができなくなります。
これにより嘘をつけない環境を作り出すことができるため、酒量をできる限り減らそうと努力をする社員も増えるでしょう。
運転手一人ひとりの意識を高めることができれば飲酒運転も減らせる可能性が高いため、その環境を作るためにもアルコールチェッカーの導入は必要なのです。
業務の負担を軽減できる
アルコールチェッカーを導入していない場合は、主に監督責任者と呼ばれる方が社員の飲酒の有無をチェックしなければなりません。
事業規模によっても異なりますが、これらの作業を毎日行うのは現実的ではありません。
また、古いタイプのものを使用している場合も、数値を手入力しなければならないなど手間がかかります。
しかし、ここ最近のアルコールチェッカー(例えば「アルキラープラス」など)はスマートフォン連動型の検知器など機能が豊富です。
検知結果もリアルタイムで閲覧でき、簡単に点呼できるというのも魅力の一つと言えるでしょう。
業務の負担を大きく軽減できるのはメリットの一つなので、アルコールチェッカーの導入はおすすめです。
おすすめのアルコールチェッカー3選
企業での飲酒運転防止対策が強化される中、アルコールチェッカーの導入は欠かせません。
しかし、種類が多く「どれを選べばいいのか分からない…」「精度や使いやすさを重視したい」と悩む方も多いのではないでしょうか?
ここからはおすすめのアルコールチェッカーを3つ紹介していきます。それぞれの特徴を比較し、企業のニーズに合った最適な1台を見つけてください。
アルキラーPlus

引用元:アプリとアルコール検知器を連動!アルキラーPlus|法人携帯スマホコム(ソフトバンク正規販売代理店)
アルキラープラスは、導入実績6,000社以上&利用継続率99.5%の実績を誇る、業界最安値のアルコールチェッカーです。スマホ連動で簡単に検知ができる手軽さと、J-BAC認定の高精度な測定が特徴的です。
アルキラープラスは、検知結果だけでなく位置情報や顔写真も取得してくれます。
データは検知した直後に管理者に送信されますので、時間や位置情報などを不正することはできません。
全く抜け道のないアルコールチェッカーとなっていますので、より正確なデータを取得し、社員が不正できない環境を作りたいと思っている事業者にもおすすめです。
料金をすぐに知りたい方はコチラ!
見積もり請求をする(無料)
あさレポ

引用元:【登録料金0円のアルコールチェッカー】アルコールチェック・アルコール検査 「あさレポ」
あさレポは、同じくアルコールチェックのクラウド管理機能として多くの企業で導入されています。
専用アプリのログイン~体温測定まで40秒で完了する操作性の高さが魅力で、運転前にサクッとアルコールチェックをすることが可能です。
初期費用、システム維持費用は無料で、定額プランと従量課金プランがあるので、企業の利用頻度によってプランが選べます。また、20日間の無料トライアルもあるので、まずは使用感を試したい企業におすすめです。
ホワイト安全キーパー

引用元:ホワイト安全キーパー公式HP
最後に紹介するおすすめアルコールチェッククラウド管理サービスは、ホワイト安全キーパーです。
こちらは以下の2つのキャンペーンを実施しているので、まだクラウド管理サービスを導入したことがないけれど興味はあるといった企業におすすめできます。
- お試し14日間無料
- サービスご契約で月額初月無料
また、アルコールチェック義務化につき早速白ナンバー事業者向けのクラウドシステムも用意されており、シンプルな操作性やスマホ連動も魅力です。
アルコールチェッカーの使い方

アルコールチェッカーを正しく活用するためには、事前の準備・設定、測定時の正しい使い方、測定データの管理・活用 が重要です。ここでは、それぞれのポイントを詳しく解説します。
事前準備と設定方法
アルコールチェッカーを正しく使用するために、まずは機器の準備と設定を行いましょう。
準備するもの
- アルコールチェッカー本体
- 付属のマウスピース(必要な場合)
- スマートフォン(アプリ連携型の場合)
- 取扱説明書
設定方法
- 電源を入れる →機器によってはウォームアップが必要な場合があります。
- 日時設定(必要な場合)→ 記録を正しく管理するために設定します。
- アプリと連携(対応機種のみ)→ スマホとBluetooth接続し、測定データをクラウドに保存できるようにします。
- マウスピースの取り付け(必要な場合)→ 使い捨てや洗浄可能なタイプがあるので、清潔に保ちましょう。
機器によっては定期的に制度を調整する必要な場合があるため、説明書を確認してください。
正しい測定方法
アルコールチェッカーの測定は、適切な方法で行わないと正確な結果が出ないことがあります。
以下のポイントに注意しましょう。
- 飲食後20分以上経ってから測定
→ 直後に測ると、口内のアルコール成分が影響し、正しい数値が出にくくなります。 - 口をすすいでから測定
→正確な数値を得ることができます。 - 機器の指示に従って息を吹きかける
→ しっかりと 「一定の強さ・時間」で息を吹き込むことが重要です。 - 測定結果を確認
→ 0.15mg/L以上にならないかチェック。 - 必要に応じて再測定
→ もし測定結果に違和感がある場合は、時間を空けてもう一度測定しましょう。
アルコールチェックは原則として対面で行う必要があります。しかし、状況により対面確認ができない場合は、運転者に携帯用のアルコールチェッカーを携帯させたうえで、対面確認と同等といえる方法で行いましょう。
データ管理と活用方法
アルコールチェッカーは、単に測定するだけでなく、データをしっかり管理し、活用することが重要です。特に、企業で使用する場合は、適切なデータ管理が求められます。
企業では 1年間の保存が義務付けられているため、データを適切に管理しましょう。クラウド連携(対応機種のみ)でスマホやPCでデータを確認できると、管理がスムーズに行えます。
さらに、運転前後の管理に活用することで、測定結果をもとに飲酒の疑いがある場合は運転を控えることができ、飲酒運転未然に防ぐことができます。
また、報告・記録のデータを管理することで、クラウド上でデータを管理・共有でき、企業全体の安全管理体制を強化し、チェックの抜け漏れを防ぐことが可能です。
このように、アルコールチェックのデータを適切に管理・活用することで、企業の信頼向上につながります。
まとめ

アルコールチェッカーの数値が0.15mg以上で車を運転すると、酒気帯び運転です。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課され、13点もしくは25点の違反点数が加算されます。
勤務する会社によっては解雇されることもあるでしょう。
車を運転する際には、アルコールチェッカーで数値をチェックすることをおすすめします。
おすすめのアルコールチェッカーは、アルキラープラスです。
多くの業界で活用されているアルコールチェッカーなので、安心して利用できます。